ミッション
岩田松雄著、発効日2012年10月7日
スターバックスやボディーショップ、アトラスなどの社長を経験し業績を上げた社長の本です。
人は何のためにはたらくのか?
こんな時代だからこそ、この部分を考えて社会に価値を出していくことが必要なんじゃないかと思っています。この本を読んでから自分がやる仕事で火花が散る瞬間はどこだろうかと考えながら仕事をするようになりました。これを意識すると何がいいかというと仕事を覚えるのはもちろんのこと自分の仕事の価値はなんなのか考えることが習慣になるので業務を覚えるのも早くなるし、イレギュラーなことがあった時に対応しやすくなります。ぜひ、一読していただきたい本です。
ー人々の心を豊かで活力のあるものにするためにー
人々の心に活力をあるものにするためには個人ではなにができるのか?
自分の仕事で誰の心に活力を与えているのかを考えることは仕事につながっている感じがします。
著者はビジョナリーカンパニーのハリネズミの概念を参考に個人のミッションにもあてはまるのではないかという考えを示しています。
※情熱を持って取り組める事、世界一になれること、経済的原動力になるもの、企業や経営者はこの3つの輪が重なり合う部分をミッション、あるいは目標にすればよいとしています。
「情熱をもって取り組める事→好きな事」
「世界一になれること→得意な事」
「経済的原動力になるもの→何か人のためになること」
何か仕事とかを考えるのに非常に参考になる考え方。
そして、いろいろ仕事をしてきていきてきてミッションはすぐにできなくてもいいし、一度構築したらそこで終わりではなく考え続けるものと言っています。変化が多い時代なので私もそれはそうだなと思います。考え続けていく事は大切だし、そのさいにこの考え方を知ってると迷わなくてすむのかなと。何か迷ったときや立ち止まった時に自分のミッション、目標を再構築するということを心にもっておけば変化に向かっていけるのかなと思います。
働くうえでテクニックやいろんな知識が必要になってくるし、覚えておくことが必要になってくると思いますが、前提としてこの何のために働いているのかということが考えられているかどうかでやはり仕事の質、人生の質も大きく変わってくると思います。それに、柔軟性が生まれると思います。知識や業務内容だけ知ってる場合とミッション教育されている場合だと同じ状況にしか対応できない。けれど、目的をしっていれば目的地に行くまでに違う手段を用いていくことができる。それがまさにスターバックスの事例として上がっています。
私が定期的に読み直すのはなぜだろうか?
考えてみた結果、知識をどんどん入れていくとミッションみたいなことを忘れてしまいそうになるから読みなおすのかなと思いました。
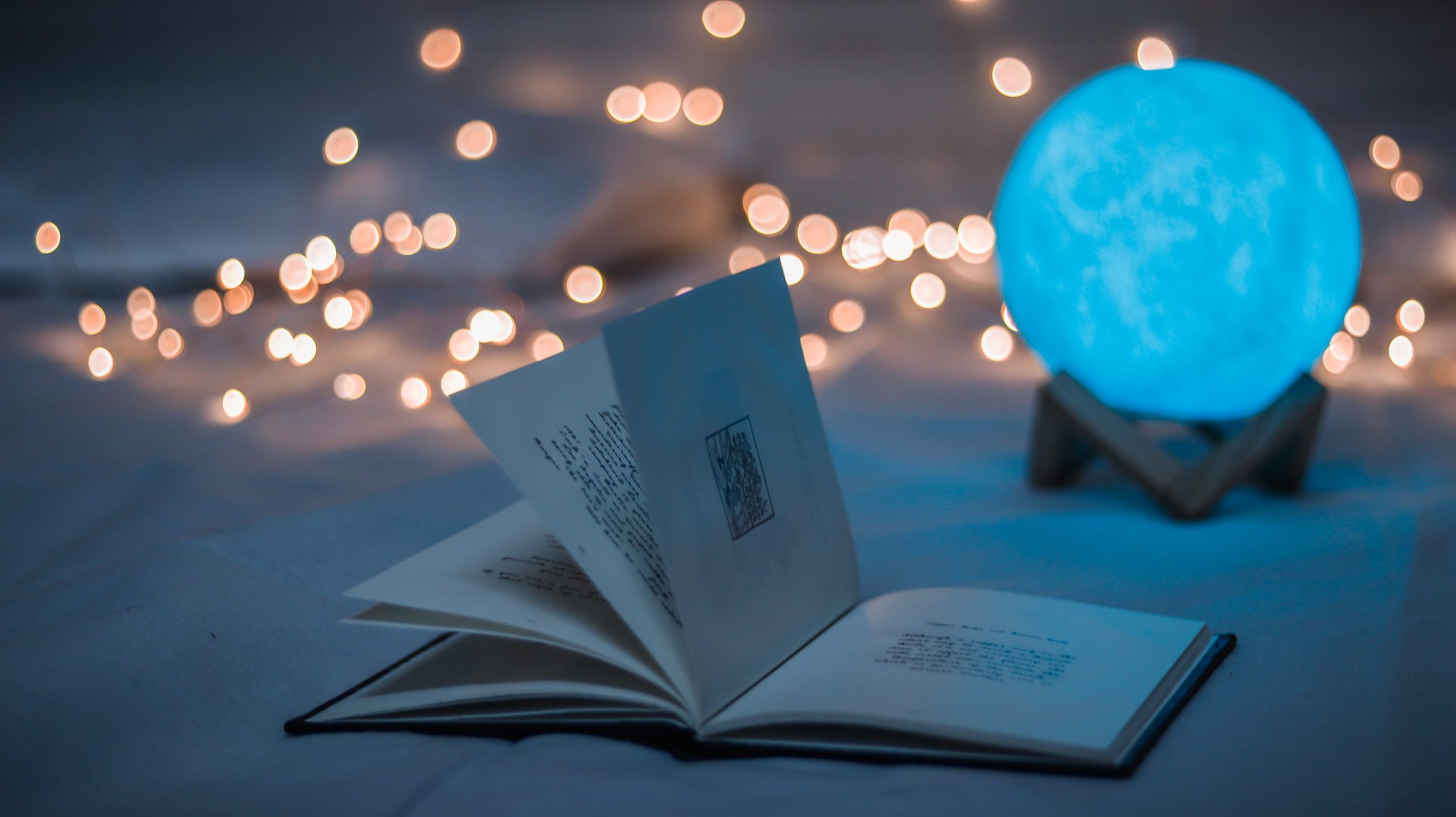
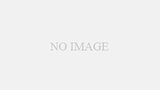
コメント